
「アースダイバー」
著:中沢新一 出版:講談社
→amazon
頭の中にあったプログラムを実行して世界を創造するのではなく、水中深くにダイビングしてつかんできたちっぽけな泥を材料にして、からだをつかって世界は創造されなければならない。こういう考え方からは、あまりスマートではないけれども、とても心優しい世界がつくられてくる。泥はぐにゅぐにゅしていて、ちっとも形が定まらない。その泥から世界はつくられたのだとすると、人間の心も同じようなつくりをしているはずである。
泥みたいな材料でできた心を「無意識」と呼ぶことにすると、この「無意識」を歪めたり、抑圧したりするのではないやり方で、人の生きる社会もつくられていたほうがいいのではないか。
中沢新一は、首都東京を縦横無尽にかけめぐり
縄文時代まで土地の記憶をさかのぼり、人が長い時間をかけてやってきたことに思いをはせる。
僕はこの本を読みながら村上春樹の小説を終始連想していた。
たとえば「世界の終わりとハードボイルドワンダーランド」。
そこで描かれている、ヤミクロに支配される闇の世界と、閉じてしまった一角獣の世界。
地下のイメージ、異界のイメージ。
たとえば「海辺のカフカ」。
ナカタさんの口から現れる白い邪悪なもの。
異界の入り口の石。
一つの境界線を引いてみる。
いやいや、意識的に引くというよりも、知らないうちに引いている境界線を意識してみること。
その境界線の向こうとこちら。
中沢新一はまず手始めに
縄文期の海岸線を地図に描く。
海岸線は境界線だ。
そこから、この物語は始まる。
「ある」と「ない」--ドーナツ状に取り囲まれた「中心」の存在。
縄文の集落はドーナツ状に集まっており、空いた真ん中「中心」は死者の場所としてあった。
岬の先端も周囲をみわたせる場所として「中心」という特性を備える。
そして、そこには神社などが建てられた。
「乾いたもの」と「湿ったもの」。
縄文期まで海だった場所は湿った場所である。
池や沼などもそこには点在する。
美しい娘の変じた大蛇の住む池。「乾いた場所」の向こう側の世界。
「湿った商品」と歌舞伎町。
「乾いた商品」と「湿った商品」。資本主義の二面性に目を向けさせてくれる歌舞伎町の存在。
生きているものと死んでいるもの。その接点が境界線上に浮かび上がる。
古代の売春は、死霊や神々の支配する、神社やお寺や聖地の近くでおこなわれた。
世俗的なタブーから自由であった場所。そこでは性さえも自由に取引される。
中沢は、性的な快楽とそれを生み出す女性の体が商品となったときから、資本主義の運動は始まったという。
商品となった性の抽象性、それは貨幣という抽象性に転じる。そうした抽象性を手に入れた時から、頭の中にあったプログラムは動き始め、世界を創造(支配)し始めた。中沢は資本主義の根源をそこに見いだす。
温泉、お湯につかること、生まれ変わること。小さな死。
そして、もう一つの「小さな死」。
セックスをして、オルガスムに達するたびに、男も女も、生きたからだのまま、少しだけ死のリアリティに触れるのである。
広々と開かれた空き地に造営される皇居。
天皇はそこから外に出で、森の中に何日も籠もることによって、野生の森のパワーを受け取っていた。
明治天皇崩御の時に、御料は京都につくられたが、御霊をお祭りする場所として
明治神宮の森がつくられた。
そして、そこは日本国家のための「鎮守の森」という象徴的な場所としてある。
富士山を中心とする視点。江戸の中心は富士山だ。
富士山を精神マップの中心にすること。
富士山の山頂から注がれる「死」の視線を感じながら生きること。
江戸の人々の心の中に少しだけ近づいてみること。
そして、そこから東京タワーについて考えてみること。
東京タワーは天へつながる橋。
橋は「端」であり、岬の先端。天に向かった岬の先端だ。
そこにも「死」という中心がみえる。
そこで、モスラの幼虫はサナギとなり成虫に羽化した。死と再生のドラマが演じられたのだ。
温泉のイメージ。
地中深く、どくどくとわき出す温泉のイメージ。
それは、全くリアルなものではなく理性を超えてしまっている世界だ。
人間の理性には、どうもなにかが決定的に欠けているらしいのである。「自然の理法」にはすんなり理解できていることが、人間の理性にはどうしたってわからないようなのだ。もちろん、理性は役にたたないと言っているわけではない。ただ、理性はどうも完璧なものじゃないらしいいので、ぼくたちには見えないところで行われている地球の営みに、もっと耳をそばだてていないといけない、と言いたいだけなのだ。
東京の谷底、谷地、谷戸は湿地帯であったが、埋め立てなど土木工事で道路に変貌した。
そこにあった、かつての水の流れは、自動車のヘッドライトの流れとして生まれ変わっていた。
そんな想像力を働かせてみること。
しかし、時代はMの時代。丸ビルに買収されたエリアはどんどん拡大してゆく。
そうした巨大開発では、そんな想像力をはたらかせなくてはならない。
そうしなくては、東京の持つ大きな魅力が損なわれてしまうことになろう。
中沢の冒険はまだまだつづく。
金魚、へら鮒、庭、苔。
苔はすでに出来上がった世界を分解して、形あるものを消滅させていく、偉大な植物の力を抽象的に象徴している。
都市の中で苔のような存在であること。
それは、路地裏にあるのではないか。
中沢は路地裏の庭園に、都市の中の「苔」を見いだす。
そして、路地裏と猫、盆栽。
首都東京から盆栽としての都市を見つけ出すこと。
大学、アジール、産学協同粉砕。権力から自由な場所としての大学。
生産者の権力から自由な死者たちの支配する空間としての大学。
それは、都市における大切な機能、大切な場所の一つだと、中沢は語る。
ファッション、境界人、婆娑羅。
人工土地、銀座。
土の匂いから遠く離れた場所。
職人の街。移住者の街。
広告の街の誕生。
商品には、たんなる実用の世界の価値を離れたところがなけらばならない。ちょっと現実を離れた部分があってはじめて、人々の無意識の欲望に触れる、魅力的な商品が生まれるのである。
銀座のホステスと新橋のコーチン芸者。
アメリカのような浅草。そこに潜む秘仏の存在。
浅草が深みに欠けなかったのは、一度もご開帳がされない秘仏の存在が大きい。
そして、ストリップと演芸の街。
しゃべくり芸とエノケン。
そこから、上野へ、秋葉原へ。
そして、下町へ。
東京の低地が持つ神話的な力。沖積層文化の世界へ。
そこは無縁の空間だった。
それも都市に必要な大切な場所。
相撲の魅力。
相撲をとおして、人は奥に怪力をひそめた自然との通路を、開こうとしてきた。
さて、ここで中沢の冒険は冒頭に戻る。
中心の不在としての東京。皇居だ。
中沢は皇居について語りながら、東京を駆けめぐってきたしめくくりとして、日本人のあり方について触れている。それについては、本文を読んでいただいた方がいいだろう。
中沢新一のこの本は、とても楽しい本だ。
それは、歴史的な事実や地質的、あるいは考古学的・民俗学・人類学的な楽しさというよりも
イメージの冒険、想像力の冒険としての楽しさが詰まっている本だといえる。
いっさいの予備知識を捨てて中沢の言葉に耳を澄ませていると
自分もアースダイビングへと身を乗り出したくなってくる。
そんなすてきな本だ。
<蛇足-1>
「アースダイビング」なる聞き慣れない言葉をはじめて目にしたのは
masaさんのブログ「Kai-Wai 散策」の記事「秋の本郷でアースダイブ」だった。その時は、不思議な言葉もあるなくらいだったのだが、「aki's STOCKTAKING」のこの本の紹介記事を読んで俄然興味がわいてきた、というわけだ。こんなにもおもしろい世界を教えてもらったmasaさんとAKiさんにはこの場を借りて感謝したい。
<蛇足-2>
この本を途中まで読んでいるときに、「フェリーニのローマ」のDVDを偶然に買ってきて見ていたら、地下鉄の工事中に古代遺跡を掘り当てるというエピソードが出てきた。まさに、アースダイビングな話だと思っていたら、この「アースダイバー」の後書きに中沢自身がこの映画の、まさにそのシーンについてふれていたのでびっくり。これは、ほんとに偶然でした。
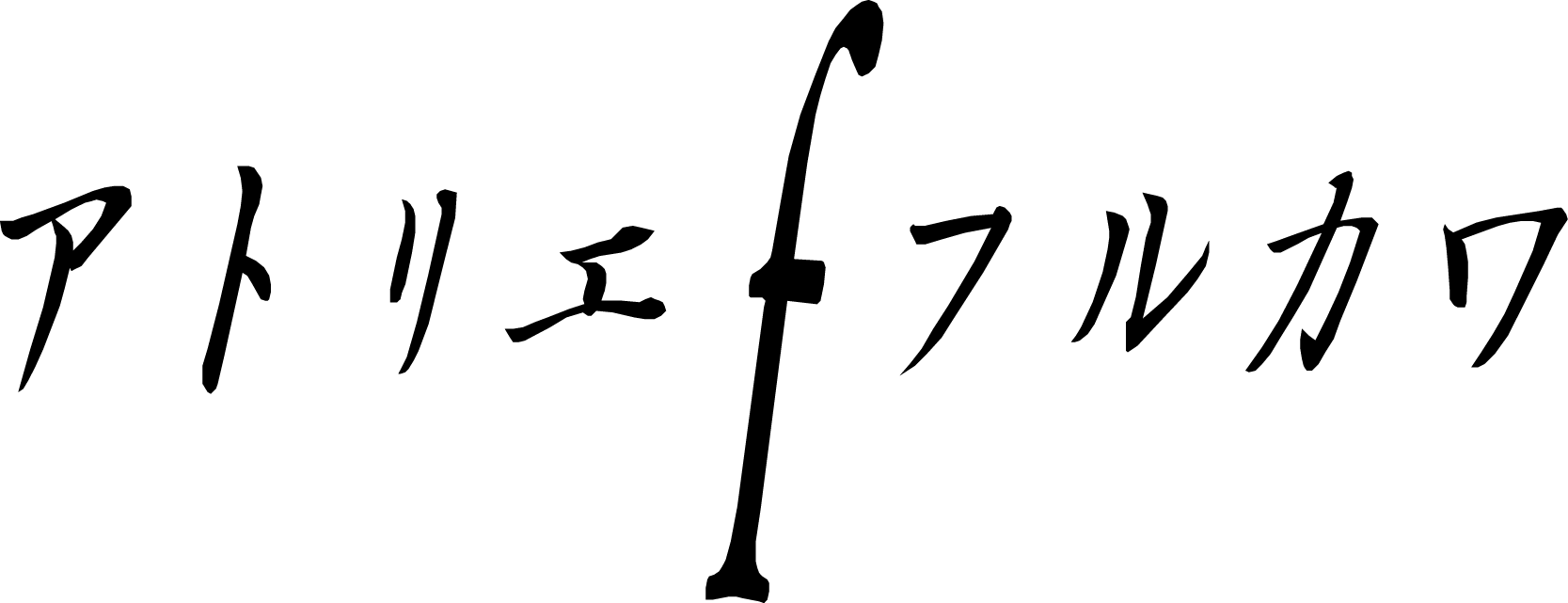
アースダイバー
中沢新一の本だから、どうせ本屋に平積みと思っていたら、最近、なかなか見つけられなかったが手に入った。5刷だそうだ。遅ればせながら読んだのだ。 アースダイバー著者…
アースダイバー、すごく読んでみたくなりました。
アマゾン行ってきまーす
中沢さんには10年前の春、四国で
偶然お会いしたことがあります。
まず最初に「キミ、ネパール人かと思った」
と言われました。
東京タワー周辺、いかがでしたか?
ヤマにヒト辺で仙、タニにヒト辺で俗、となりますが、やはり高いところにはそれなりのヒトが住みたがるようです。
和辻・オギュスタンベルク・中沢新一・澤田允茂・岩村和夫・永田一征
研究計画書を、院試とその後に続く、修士論文の為に作成しました。
その為に読み込んだ文章やら、書籍の主要なものが下記のこれら。
実際は…
糸井、中沢、タモリの対談が面白い。
http://www.1101.com/nakazawa/2005-09-20.html
etienneさん こんにちは
東京タワーって、なんだか、不思議な力を持っていますよね。
幼少の頃、東京旅行で最初に目にしたときから
僕は東京タワーにとらえられていたことを、
この本を読んで気がつきました。
第9回桑原武夫学芸賞アースダイバー
第9回桑原武夫学芸賞が、
中沢新一さんの「アースダイバー」に決まりました。
中沢新一さんは、「チベットのモーツァルト」で
第6回(昭和59…