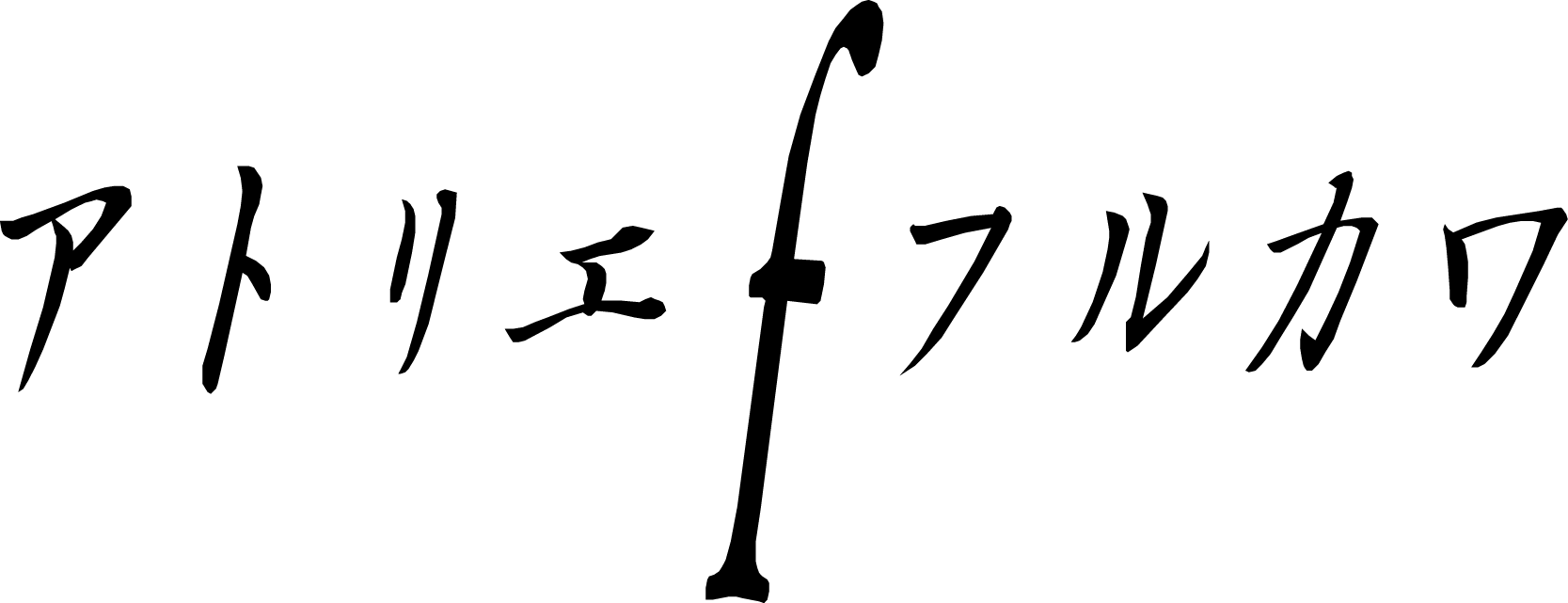「新築物語」
著:清水義範 発行:角川書店
→amazon
清水義範。軽快で、ちょっとしゃれていて、なかなか巧みな文章で、時々日本語を考えさせられる。そんな文章を書く。うちの家内が好きなのだが、僕も負けずに好きだ(!)、といっておきたい。
その清水さんが家をつくる話を書いたのがこの本だ。ホームページに載せていた書評から転載する。
---------------------------------------------------------------------------
タイトル通り、40代前半か30代後半の夫婦が家を新築するお話。
話は奥さんのお母さんが亡くなるところから始まる。のほほんとした洒落の効いた小説を得意としている作者のイメージにしては、少々緊張感のある雰囲気から始まるが、家の新築にはこのようなテンションが付きまとうことが多い。というのも、家を建てるというのは一世一代の大仕事、失敗するわけにはゆかない。そして、たいていは一度きりの経験となる。だからみんな必要以上に慎重にならざるを得ない。自分たちよりも先に家を建てた人の意見を聞いたりするのだけれど、この大事業を実現するのに必要なお金の額が一桁も二桁も違うから、たいていは銀行などから多額の借金を迫られる。借金なんて、しないでよければしないほうがいい。だから家を建てることは清水の舞台から飛び降りるようなところが付きまとう。清水の舞台から飛び降りるなんてとっても緊張感がある。逆にいうと緊張感がなくては家は建てられない。でも、そんな緊張感を自らに引き起こすのには何かきっかけがないとなかなか・・・・。
というわけで、変な話だが、家を建てられる方で、身内の人間が亡くなるということをきっかけとしているかたは少なくない。そして、この夫婦もそんなことをきっかけとして家を建てる決心をする。もし、お母さんが亡くならなかったら?きっと彼らは家を建てることを考えなかっただろう。人生そんなものかもしれない。
彼らが最初に直面した問題は、お母さんが一人で住んでいた家が借地の上に建っていてその借地権がちょうど切れたところであった、ということ。借地権を地主に買ってもらって新天地を探すか、借地権の更新をしてその土地に住みつづけるか。何と大きな問題だろう。家は土地の上に建っていて、人間はその家で生活をし人生を刻む。だから、家にも愛着はあるしその土地にも愛着はある。彼らは試行錯誤、けんけんがくがくをくり返し、最終的に借地権を更新し、お母さんの家をとり壊して自分たちの新居を建てることにした。この辺のいきさつについては本を読んでいただくとして、僕のようなものにとってはなかなか参考になるような内容だった。
そして、家を新築する事に決めたとき、彼らは相談に乗ってくれる人を選んだ。おじさんにあたるその人は、大手ハウスメーカーで設計部長まで勤めた人物。その経験と知識はあてになるし、おじさんの七光で手抜き工事などされる心配もない。しかし、あくまでおじさんのいた会社はハウスメーカー。そこには、ハウスメーカーなりの家づくりしかない。こんなやり方で納得できるの人はどのくらいいるのかなあ、とつい考えてしまう。このへんは反面教師的にこちらも勉強になる。それにしても、彼らが出会っていたアドバイスしてくれる人物がハウスメーカーのステレオタイプな進め方に疑問を持っている設計事務所の人物であったらどうなっていただろうか?たぶん、まったく違った家ができていた、のではないか。その違いについて想像を巡らす、そんな小説だった。