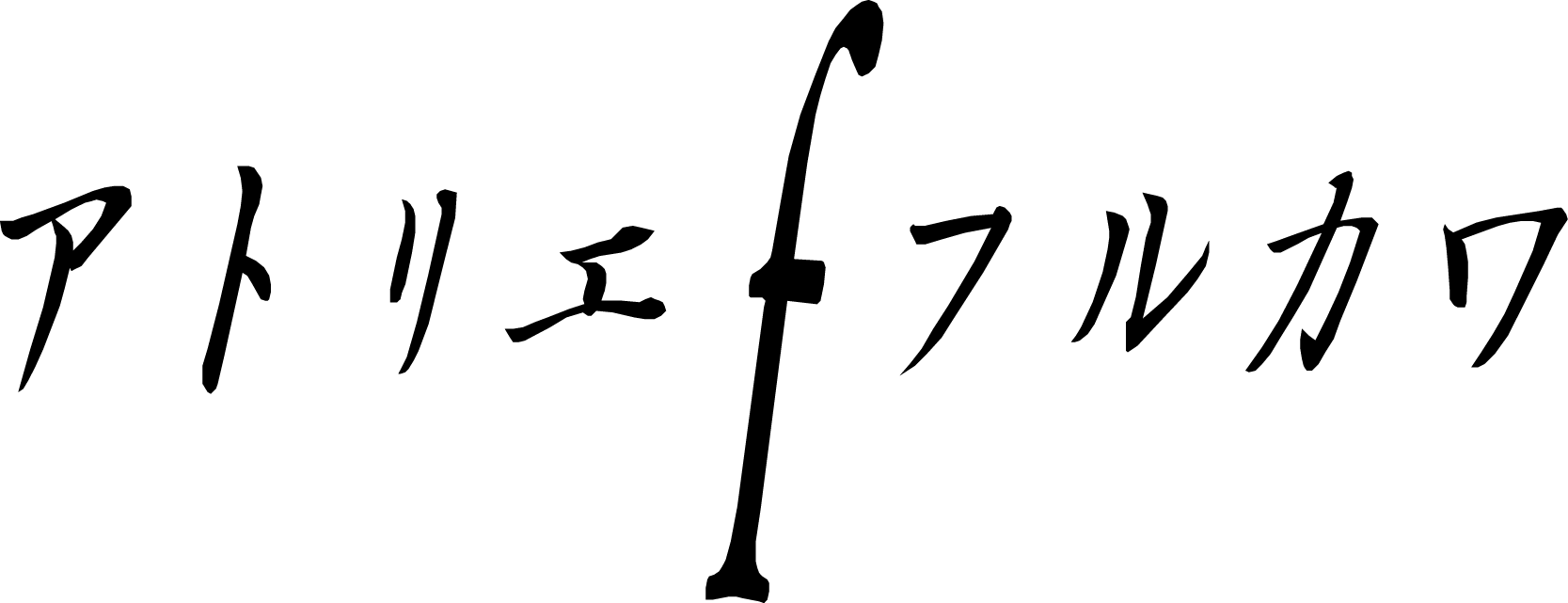「翻訳夜話」
著:村上春樹・柴田元幸
文春新書 定価:740円+税
→amazonで詳しく見る
翻訳という作業について村上春樹と柴田元幸が行った、
三つのワークショップの記録に
レイモンド・カヴァーとポール・オースターの短編小説を
両者が訳したテキスト(+原文)を加えて一緒にした本です。
以前のエントリー三浦雅士の「村上春樹と柴田元幸のもうひとつのアメリカ」で、
「翻訳」という作業に強い関心をもち、「住宅設計」との類似性について考えたことを書きました。
そこで、「翻訳」というキーワードを、「住宅設計」に関連させて
もっと掘り下げてみようと思いこの本を読んでみました。
最初にふれておかなくてはいけないのは、
この本で村上春樹が「翻訳」と「創作」はまったく別のものであるとはっきり言っていること。
村上春樹は、そこにはっきりとした線を一本引いています。
そして、ここでの僕の論点は、僕が考える住宅の設計について、村上・柴田のいうところの「翻訳」という作業に類似点を見いだし、それを検証することです。
けっして「翻訳」の一般論について論考するわけではありません。
小説を書くという世界は、住宅を設計するという世界とは大きく異なります。
しかし、そこに「翻訳」というキーワードが加わるとこのふたつの世界はぐっと近づきます。
両者の類似性について僕が考えるところについて最初にふれておきましょう。
住宅の設計には、住まい手がいます。翻訳には原作があります。
どちらも、設計者・翻訳家にとって厳然とした存在としてそこにいる(ある)わけです。
設計者・翻訳家とも住まい手・原作がまずあって作業が始まります。
設計者は住まい手の要望を聞きそれを形にしてゆきます。
翻訳家は原作を読んでそれを別の国の言葉に置き換えます。
右の瓶から左の瓶へ水を移し替える、言ってみればそういう作業ととらえられます。
その点で小説を書くと言う行為(=「創作」)が「翻訳」とはまったく違うものであると
村上春樹は言うわけですね。
しかし、僕がここで注目するのは
一見、機械的に見えるこれらの作業に「創作」の種がひそんでいる、
「創作」の種がこっそり植えられているということなのであり、そのことについて村上と柴田はかなり意識的だということなのです。
村上春樹と柴田元幸の「翻訳」という作業について語っている言葉が僕にとって刺激的なのは、「翻訳」という作業の過程で生まれる「創作」について、彼らが意識的に語ってくれている部分でなのです。そして、僕が彼らの「翻訳」に関する本を読む意図も、そうした言葉を読み込むことなのです。
いくつか引用してみましょう。
「村上:とにかく相手のテキストのリズムというか、雰囲気というか、温度というか、そういうものを少しでも自分のなかに入れて、それを正確に置き換えようという気持ちがあれば、自分の文体というのはそこに自然にしみ込んでいくものなんですよね。自然さがいちばん大事だと思う。だから、翻訳で自己表現しようというふうに思ってやっている人がいれば。それは僕は間違いだと思う。結果的に自己表現になるかもしれないけれども、翻訳というのは自己表現じゃあないです。自己表現をやりたいなら小説を書けばいいと思う。」(p36)
「村上:僕が言っているいちばん大事なことというのは、たとえばここにテキストの文章がありますよね。そしてあなたはそのテキストがすごく好きだったとしますよね。そこに重要なセンテンスが一つあって、このセンテンスの本当の意味は俺にしかわからないはずだという、そういう深い思い入れがあったとしますよね。そういうものがあなたの中にあれば、そのほかのいろんな複雑な問題も、いつしか結局は解決してゆくだろうと、僕は楽天的に信じているわけです。それは自信という言葉とはちょっと違うんだけどね。親密で個人的なトンネルみたいなものが、そのテキストとあなたの間にできれば、それは翻訳という作業が原理的に内包する避けがたい誤差を、うまいかたちで癒してくれるかもしれない。」(p41)
「村上:原作者の心の動きを、息をひそめてただじっと追うしかないです。もっと極端に言えば、翻訳とはエゴみたいなのを捨てることだと、僕は思うんです。うまくエゴが捨てられると、忠実でありながら、しかも官僚的にはならない自然な翻訳が結果的にできるはずだと思います。」(p62-)
「村上:僕は翻訳というのは、基本的には誤解の総和だと思っているんですね。だから、一つのものを別の形に移し換えるというのは、ありとあらゆる誤解を含んでいるものだし、その誤解が寄り集まって全体としてどのような方向性を持つかというのは、大事なことになってくると思うんですよね。僕は、そういう方向性というのを「偏見」という言葉である程度置き換えちゃっているわけで、偏見という言葉はあまりよくないんだけれど・・・。いろんな誤解があって、たとえ誤解の総量が少ないにしろ、そのひとつひとつの誤解がそれぞれ違う方向を見てたら、できた翻訳というのは、あまり意味がないと僕は思うんですよ。だから、たとえ偏見のバイアスが強くても、それが総体としてきちっとした一つの方向性さえ指し示していれば、それは僕は、翻訳作品としては優れているという風に思うんですよ。」(p192)
ずいぶん長い引用を何ヶ所もしてしまいましたが
ここで村上春樹が語っている「テキスト」を「住まい手」もしくは「すまい手の要望」、「翻訳」を「設計」と置き換えて読んでみるということなんですね。
住まい手の要望を実現するという設計という作業から創造的な空間が生まれること。
「翻訳」とは、ただ機械的に言葉を移し換えているだけではないということ。
同じく「設計」とは、ただ機械的に住まい手の要望を形に移し換えているのではないということ。
そこには「人」がいるということ。それゆえに創造的な瞬間が生まれるということ。
これからも、「住宅設計」と「翻訳」については考えてゆくつもりでいます。